 教養
教養 世界三大美女はどうやって決めた?時代と地域で異なる美の基準とは?
日本ではクレオパトラ、楊貴妃、小野小町が世界三大美女とされています。しかし、他の地域では全く異なる名前が挙げられることも少なくありません。その理由は地域により美女のの選出基準が異なるためです。また、美に対する価値観も時代とともに変遷しています。
 教養
教養  教養
教養  教養
教養  教養
教養  教養
教養 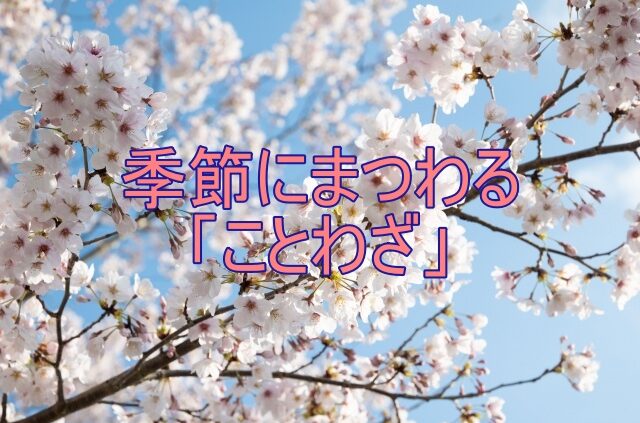 教養
教養  教養
教養  教養
教養  教養
教養  教養
教養